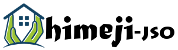商業・法人登記とは
商業・法人登記とは、会社や法人(社団法人など)について、設立手続や様々な変更事項、例えば役員変更、目的変更、本店移転などが生じた場合に、法務局へ変更手続きを行うものです。平成18年に新会社法 が施行されたことにより、近年では、有限会社から株式会社への移行、合併・会社分割等の組織再編などといった案件も増えてきております。じっくりお話を伺った上で、お客様のニーズに応じた手続きをサポー トさせていただきます。

会社設立登記
会社を設立するためには、法務局にて登記を申請しなければなりません。
設立は、平成18年の会社法施行によりハードルが低くなりました。
- 資本金1円の会社設立も可能となりました
※1円で登記ができるという意味ではありません! - 役員は取締役1名のみでも可能となりました。
- 役員の任期を約10年まで延長できるようになりました。
- 類似商号の制約が緩くなりました
また、当事務所では電子定款に対応しておりますので、会社の設立費用を4万円節約していただくことが可能です。
当事務所にご依頼していただければ、会社名と取締役が決まっていれば1週間後に会社を設立させることも可能です。
会社設立については赤松大賀司法書士事務所にお任せ下さい!
株式会社設立登記手続きの流れ

事前お打ち合わせ
(a)商号、(b)本店、(c)事業目的、(d)資本金、(e)発起人(出資者)、(f)役員(代表取締役・取締役・監査役など)、(g)事業年度などお話をお伺いしながらアドバイスを致します。
![]()

必要な書類を作成します
当事務所で書類を作成し、内容をご確認いただいた後、発起人・役員などから署名や押印をいただきます。
![]()

公証役場にて定款認証
当事務所では電子定款に対応しておりますので、印紙代(4万円)を節約することができます。
![]()

出資金の払込
発起人から出資金を払い込んでいただきます。
会社法施行後は、資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました。
![]()

法務局への申請
当事務所にて、管轄法務局へ登記申請を行います。
法務局に登記申請をした日が会社設立の日になります。
![]()

会社設立登記完了
STEP5の登記申請後、しばらくすると登記が完了します。
登記完了後に登記事項証明書を取得して、申請どおりの登記ができたことが確認できれば手続が完了です。
また印鑑証明書も会社設立から取得できるようになります。
役員変更登記
役員が就任、再任(重任)、辞任などにより退任したとき・代表取締役など住所を登記すべき者の住所を変更したとき。その変更から2週間以内に、変更登記を申請しなければなりません。
役員変更登記の大まかな流れは次のとおりです。
役員変更登記の手続きの流れ

事前お打ち合わせ
現在の会社定款をご準備いただき、ご相談下さい。
株主総数もお打ち合わせの際に、伺いますので株主名簿等現在の株主様の総数、住所、氏名、持株数が分かるものもご準備下さい。
![]()
![]()

株主総会などの招集手続き
役員を選任するため、会社の定款の規定に基づき、株主総会を招集します。総株主の同意がある場合など、招集手続きを不要にできる方法もあります。
また必要に応じて、代表取締役を選定するために取締役会を開催します。
![]()

役員の選任
株主総会や取締役会にて役員を選任します。議事録作成のご依頼も受けたまわります。
![]()

その他添付書類の取得・準備
登記内容によって、役員の印鑑証明書などが必要な場合があります。
事前に必要書類をお伝えしますので、ご準備ください。
![]()

法務局への申請
当事務所にて、管轄法務局へ登記申請を行います。
※役員変更登記は変更があったときから2週間以内に行うこととなっています。
![]()

役員変更登記完了
STEP5の登記申請後、しばらくすると登記が完了します。
登記完了後に登記事項証明書を取得して、申請どおりの登記ができたことが確認できれば手続が完了です。
法改正により、平成27年2月27日(金)から、役員変更登記の添付書面が増えました
<改正点の内容>
- 設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている住民票等の市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付することとなりました。
※ただし、もともと印鑑証明書を添付する取締役等は不要です。 - 法務局に印鑑登録している代表取締役等が辞任するとき、辞任届に実印の押印と印鑑証明書を添付するか、印鑑登録している代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付することとなりました。
- 役員の婚姻前の氏をも申出により登記することができるようになりました。
また、監査役の会計の範囲を会計に限定している場合は、登記が必要となりました。
平成18年3月31日以前に設立された会社で、定款に「株式譲渡を制限する」旨の規定を置いている会社は該当する可能性が高いです。
ほとんどの中小企業がこれに当てはまる可能性がありますのでご注意ください。
この登記は、平成27年2月27日以降、最初に監査役が就退任(重任を含む)するまでに行う必要があります。