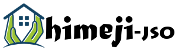見守り契約
いざと言うときに備える継続的な見守りサービス
見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうための契約です。 見守り契約を結ぶことにより、判断能力が十分あるうちから、定期的に会ったり、連絡をとりあったりすることで、健康状態や生活状況を確認してもらうことができます。
また、支援する人は見守るだけではなく、見守りながら、定期的にコミュニケーションをとり信頼関係を築くことにより、本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極めることができるのです。
任意後見契約を結んだときには、本人にも判断能力がありますが、実際に任意後見契約がはじまるのは、本人の判断能力が衰えてからのことになります。
 見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。 また、定期的にコミュニケーションが取れない状況であれば、直接、本人の判断能力の衰えを確認することができなくなるため、適正な時期に任意後見契約の効力を生じさせることがむずかしくなってしまいます。
見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。 また、定期的にコミュニケーションが取れない状況であれば、直接、本人の判断能力の衰えを確認することができなくなるため、適正な時期に任意後見契約の効力を生じさせることがむずかしくなってしまいます。
そこで、任意代理契約(財産管理委任契約)まで必要はないと考える場合でも、任意後見契約とセットで結んでおきたいものが見守り契約なのです。
任意代理契約(財産管理委任契約)

任意後見がスタートする前支援が必要な方は
任意後見制度は、判断能力が低下してからしか利用できません。しかし、高齢になってきてこれまでのように体が動かない。役所などからたくさんの書類が届くようなってきたが、何が大事か分からない。今は認知症じゃないけどいろいろ相談に乗ってもらいたい。
任意代理契約(財産管理委任契約)は、任意後見がスタートする前でも、特定の人に代理権を与えて、契約に従って様々なことを支援してもらうことができます。
財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理などが任意代理契約の内容として盛り込まれることが多いです。しかし、任意後見の内容と同一である必要はありません。
死後事務委任契約
死後の気がかりをなくしたい

死後に親族に迷惑をかけたくないとき、近くに自分のなくなった後のことを託せる人がいないとき、葬儀は?遺骨はどうなるの?借りている家は?病院代や施設料の支払いは?様々なことが心配があると思います。
残念ながら、行政がそれらのことをやってくれるわけではありません。生前に葬儀会社の葬儀プランに入っていても誰が喪主になって葬儀を主催しているれるのかという問題もあるでしょう。
死後事務委任契は、自分が亡くなった後の自己の死後の葬儀や埋葬等といった事務を託し、託した内容に沿って事務を委託する契約をいいます。
委任できる内容としてはたとえば次のようなものがあります。
1 遺体の引き取り
2 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
3 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
4 自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
5 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
6 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
7 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
相続はどんな方でも生じる問題です。そしてこの問題は財産の有無にかかわりありません。特に近年は、核家族化によって、身寄りがないままに亡くなる方も増えているように感じます。
遺言や任意後見制度とあわせて利用することで、気がかりの多くを減らせれるでしょう。
費用
| 見守り契約書作成 | 54,000円 |
| 任意代理契約書作成 | 54,000円 |
| 任意後見契約書作成 | 216,000円 |
| 見守り契約 | 月額 6,480円 |
| 任意代理契約 | 月額 32,400円~ |
| 任意後見契約 | 月額 54,000円~ |